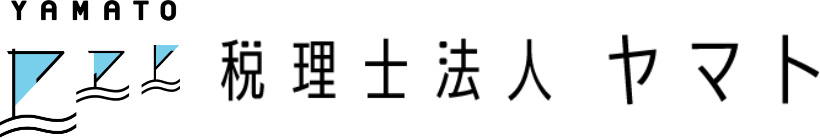Contents
相続手続きだけでも大変ですが、相続税の申告と納税が必要な場合には、10ヶ月という期限があります。
期限内にすべてを終えないとペナルティが発生したり、特例や控除などが使えないと想定以上の相続税を納税する必要があります。
相続税の相談から申告が完了するまで、何度も顔を合わせて打ち合わせ等をしますので、ご自身にとって安心できる専門家を選んで一緒に進めていきましょう。
本記事では、福岡県内で相続税の相談をしたい方へ、相談先の選び方や初回面談へ向けた準備などをご紹介していきます。
相続税の相談窓口3選|特徴と使い分け
旦那さまが亡くなられたあと、葬儀や四十九日の対応をしたり、あいさつ回りや役所関係の手続きをしていると、あっという間に3ヶ月が経過している頃かと思います。
相続税の申告が必要な場合には、亡くなられてから10ヶ月が期限ですので、亡くなられてから3ヶ月が経過していれば残り7ヶ月で完了させる必要があります。
もし、6ヶ月を過ぎていたら間に合わない可能性がありますので、急ぎ相談をしましょう。
いずれにしても、相続税の相談は税務署や税理士会にすべきか、インターネットで検索した際に表示された税理士に相談すべきか迷いますよね。
まずは各窓口の特徴を把握したうえで、相続専門の税理士との初回面談を起点に進めるのがおすすめです。
窓口➀:税務署(無料相談)
税務署は国の機関ですので、相続税に関する基本的な相談にいつでも無料で対応してくれます。
相続税の申告を最後までご家族のどなたかがやりきる場合には、何度相談をしても無料で対応をしてもらうことができますが、相談できる内容が限定されていることと、毎回必ず予約を取ってから相談に行かないと相談に応じてもらえません。
ただ、繁忙期以外であれば電話での対応もしてもらえる点は他にはないサポートです。
以上のとおり、税務署は同じ担当者がずっと対応してくれることもなく、財産や相続人の全体把握や管理はおこなってくれません。
あくまで、聞いたことについて、聞いた範囲内での回答をする役割になります。
相続税の納税額が少額であれば自力対応も選択肢ですが、それを超える場合にはやはり税理士への相談がおすすめです。
税務署に相談する場合は事前予約のうえで向かいましょう。繁忙期(1〜3月)は特に注意が必要です。
窓口➁:税理士会の無料相談会
全国に15団体の税理士会があり、税理士はいずれかの税理士会に所属しています。
この税理士を束ねる税理士会が主催する無料相談会が定期的に開催されます(税理士記念日周辺など)。
直接税理士に会える貴重な場ですが、時間は短く、必ずしも相続専門の税理士に当たるとは限りません。
無料相談は入口として有効ですが、具体対応は個別の面談で深掘りする前提で準備して臨みましょう。
窓口➂:税理士法人の面談相談
相続専門・相続に強い税理士では、初回から有料面談(多くは60分)を採用する事務所が増えています。
相続人・財産の情報を持参すれば、具体的な試算や不動産評価の見立て、適用可能な特例の方向性まで踏み込めます。
結論として、「方向性の確定」と「担当税理士との相性確認」のために、面談相談の活用が最短です。
相続税の相談前に準備すべき書類

相続税の相談を効率的に進めるためには、相続税のアドバイスに必要な書類を事前に準備しておくことが大切です。
特に初めて相続手続きを行う方は、どの書類が必要なのか分からず不安を感じることが多いと思います。
専門家との面談をスムーズに進めるため、亡くなられた方・相続人・不動産関連の書類や入手方法をご紹介します。可能な範囲の準備で構いません。
亡くなられた方に関わる書類
「戸籍関連」「財産関連」の2系統が揃うと、面談の精度が一気に高まります。
どのみち申告で必要になる資料ですが、税理士と契約後は連携専門家を通じて代理取得できるものも多いため、無理のない範囲でOKです。
<戸籍に関わる書類>
相続人を法的に確定するため、出生から死亡までの戸籍等が必要です。
取得が難しい古い戸籍は専門家依頼が現実的です。まずは想定相続人の関係図を作り、不明点は面談で共有しましょう。
<財産に関わる書類>
預貯金、不動産、株式、生命保険、借入などを一覧化し、可能な証憑を揃えます。
郵便物やカード明細にも手掛かりがあることが多いので、完了まで保管がおすすめです。
相続人に関わる書類
最終的には戸籍・住民票・印鑑証明等が必要ですが、初回は一覧や関係図でも構いません。
未成年者や代襲相続、連絡が取れない相続人がいる場合はその旨を共有してください。
不動産がある場合の追加情報
相続税評価では、地形・接道・周辺環境等で減額要素が生じます。小規模宅地等の特例の適用可否も要検討です。
面談では固定資産税評価証明書(または課税明細書)をご持参ください。登記事項証明書があれば所有関係の確認が迅速です。
賃貸中なら賃貸契約書や収支状況も合わせて用意すると精度が上がります。
相続税の相談から申告までの基本的な流れ

相続税の申告は、亡くなられてから10ヶ月以内に完了させる必要があります。
初めて携わる方には短く感じられます。国税庁資料では相続税申告の約85%で税理士が関与しており、実務は専門家起点が一般的です。
初回面談で依頼先を選定
面談で最初に確認するのは「申告が必要かどうか」。
基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えれば申告必須です。相続人と財産の概況がわかれば判断可能です。
申告完了まで打合せは多くなりますので、相性・説明の分かりやすさ・不動産評価の力量などを面談で見極めましょう。
親身さ、担当一貫性(面談担当者=実務担当者)、不動産評価の経験値は重要な判断軸です。
懸念があれば、別事務所の面談も受け比較しましょう。
支援範囲と見積書の確認
面談後は契約内容と概算見積を受領し、範囲と透明性を確認します。
追加の財産発見などで費用が動くこともあるため、どの条件で変動するのか事前に明確化が必要です。
見積が「申告のみ」か、「書類収集・名義変更等まで含む連携体制」かも要チェックです。司法書士・行政書士との連携実績があるとスムーズです。
福岡エリアにも連携が強くスムーズな事務所は多数あります。初回面談で見極めていきましょう。
面談・見積を踏まえ依頼先を最終決定
相続専門の税理士は知見に応じた報酬帯が一般的です。価格だけでなく「総額最適(税理士報酬+相続税を合わせた合計の最小化)」で判断しましょう。
同じ条件でも評価・特例選択で結果が変わるのが相続税。安価に惹かれて結果的に税額が高くなるケースに注意です。
開始後は期限遵守で申告へ
申告期限(10ヶ月)は延長不可。期限超過は特例喪失や加算税等のリスクがあります。
相続人確定・財産確定・不動産現地確認・遺産分割協議など、やるべき作業は多岐にわたります。
分割協議が長引くと全体スケジュールに影響します。専門家の進行管理のもと、期限内完了を目指しましょう。
【おすすめ】相続税の相談は税理士法人ヤマトへ
税理士法人ヤマトでは初回から有償の面談(11,000円/税込・1時間、延長料金なし)を採用しています。
営業的な無料面談ではなく、「状況を丁寧に伺い、専門的知見を具体的に提供する」ための対価として設定しています。相続税で差がつきやすい不動産評価に自信があり、奥さまにも安心の女性税理士が分かりやすくご説明します。平日夜・土日祝の面談にも対応(福岡市内・アクセス良好)。
初回面談で方向性と優先順位を明確化し、期限内の申告完了まで伴走いたします。