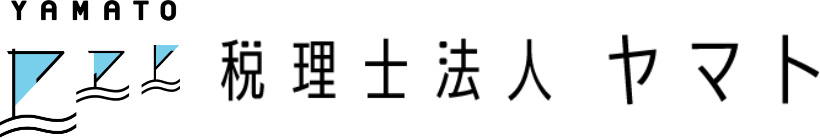Contents
福岡市内で相続に困っていてよい相談先が無いかな、と思って調べていたら「相続相談所」のような文字を見つけて、どんなところだろうかと思って検索されているのではないでしょうか。
福岡市内だけでも相談ができる場所が多く、インターネットで調べるとさらに増えるため、はじめての相続の場合どこに相談したら良いかとご不安になりますよね。
「相続の相談ができる場所」=「安心して相続の相談ができる税理士法人」と読み替えていただき、「相続に強い税理士法人」を探すと出会える可能性が高まるかと思います。
相続に強い税理士法人で、日々相続税の申告をはじめとした相続業務を中心に担当している税理士が、はじめて相続を経験する方が相談先選びの不安を解消できるようにQ&A形式で10個のポイントを解説していきます。
なお、当法人の面談は初回から有償(11,000円/税込・1時間、延長料金なし)です。営業目的の無料面談ではなく、目の前のお客様に正面から向き合い、専門的な助言を提供するための対価としてご理解いただければ幸いです。
ぜひ、良い相談先選びに活用していただければと思います。
相続に強い税理士法人が安心できる相続相談所である理由

国税庁が公表しているデータによると、毎年の相続税の申告において、税理士が関与している割合は85%以上という結果になっています。
税金関係ですので税理士が関与している割合が高いということになりますが、インターネットで調べてみると財産の金額によって報酬は変わるものの、少なくとも25万円以上の税理士報酬が発生するケースが多い中で、これだけ多くの方が税理士に依頼している点は驚きではないでしょうか。
税金関係は法的にも税理士以外への相談はできませんが、決して安いとは言えない金額です。
実際に自分たちでやってみようと試みる方は多いと思いますが、難しい点や複雑な点も多く不安になってきますので結果的に税理士へ依頼しているケースが多いという状況になっています。
では、25万円以上の報酬を払うとしたら、実際にどんな税理士を選ぶと良いのでしょうか。
それは「相続に強い税理士」です。
税理士にも得意な分野と苦手な分野がありますし、日ごろ企業の会計を支援している税理士からすると年間に0件~3件程度のケースが多く、相続の経験値が少ないため調べながら対応することにもなります。
一方で、相続に強い税理士は、日々の業務で相続税の申告に携わっており、年間で10~20件ほどの対応をしており、相続時の節税対応や不動産の評価なども得意な業務となっています。対応件数だけでなく、どれだけ「親身(自分ごと)」「網羅的(相続人の相続対策まで考慮)」「丁寧(相続人が分かり易いように説明)」「節税(選択肢を相続人に提示し納得を得た上で節税)」をしてもらえるかが大事なことです。
「相続専門の税理士法人」「相続に強い税理士法人」というキャッチを出している税理士法人であれば、おおよそ安心して依頼できると思いますが、「不動産に強い」「土日・祝日・平日の夜などに対応可能」などの追加のメリットと、お話をして相性が良いことが安心につながります。
その他のご不安な点について、ここからQ&A形式でご紹介していきます。
【Q&A1-3】相続の手続きで最初に確認したいこと

相続が開始されたあと、相談先を選定したり初回有料面談の前にやっておくと良い内容をQ1~Q3にまとめました。
Q1:相続手続きの最初の相談はいつごろまでにした方がいいですか?
相続手続きについては、亡くなられてから3ヶ月以内に相続放棄の有無の判断が必要となり、相続税の申告がある場合には10ヶ月、2024年から相続した不動産の名義変更が3年以内という期限があります。
本来は相続放棄の前である亡くなられてから2ヶ月以内に専門家へ相談することが理想ではありますが、四十九日の法要が終わっていると2ヶ月が経過し3ヶ月の期限目前またはすでに3ヶ月が過ぎてから探しているケースが多くなります。
相続財産を放棄せずに相続することを決めていれば特に3ヶ月以内の手続きは発生しないため、相続放棄をしないという決断ができればこの3ヶ月という期限を過ぎてからの相談でも構いません。
ただし、相続税の申告がある場合には10ヶ月以内に申告と納税を済ませなければならないため、3ヶ月を過ぎていると意外と慌ただしいスケジュールになります。
不動産と預貯金で3000万円ほどの財産がありそうな場合や、相続の進め方について全く分からない場合には、亡くなられてから3ヶ月を目安に一度相談しておくことで、そのあとのスケジュールに余裕がうまれます。
Q2:どのような財産が相続の対象になりますか?
亡くなられた方の財産がどのくらいなのかで、相続税の申告の有無が決まってきます。
初回面談に行っても財産が全く分かりません。という状況だと、せっかくの面談の機会が活かせずにもったいないです。
主に、プラスの財産として、土地・建物、預貯金、有価証券、現金について整理しましょう。
また、ローンや借金や未払いの税金などのマイナスの財産も相続の対象となりますので、こちらも整理しましょう。
その他、名義預金と呼ばれる計画的な贈与がないか、亡くなられた日より3年以内の贈与財産がないか、生命保険や退職金がいくらなのかもチェックしておきましょう。
上記の財産がすべて把握できなくても、土地や預貯金・有価証券などがおおよそ把握できていれば、相続税の申告の有無が判断できます。
Q3:相続手続きの主な流れを教えてもらえませんか?
相続手続きは主に次の6つのステップで進んでいきます。
➀~➂は資料の収集や手続き、調査などが主体ですので、どなたかが積極的に推進すればうまく進みます。
➃は相続財産をどのように分割するかを決めるため、この時点で揉める可能性があり、最も重要なポイントといえます。
➃が決まれば、➄➅は専門家に依頼してしまえば対応が進んでいきますので、比較的スムーズに進めることができます。
【Q&A4-6】税理士に相談するメリットと費用感

税理士の選び方はQ&Aの9~10でご紹介するとして、そもそも税理士に依頼するメリットや費用感についてのQ&Aを確認していきましょう。
Q4:税理士に相談するとどのような安心感が得られますか?
相続に強い税理士は、おおよそ年間に10〜20件の相続に携わっており、仕事の多くが相続税の申告が必要な方に対するサポートや相談に乗っている状況です。
冒頭にも記載しましたが、相続税の申告においては85%以上が税理士に依頼しています。
相続税の申告をするにあたって安心感が得られるポイントはいくつかありますが、主なポイントは次のとおりです。
Q5:相続税申告の費用の目安はどのくらいになりますか?
相続税申告の税理士の報酬は、一般的に遺産総額の0.5%から1.0%が相場となっています。
具体的な報酬例は、単純な試算としてはこちらになりますが、あくまで一例ですので各税理士法人ごとに異なる報酬を確認しましょう。
| 遺産総額 | 5,000万円未満 | 20〜50万円 |
| 遺産総額 | 5,000〜7,000万円 | 25〜70万円 |
| 遺産総額 | 7,000万〜1億円 | 35〜100万円 |
大切なことは、税理士報酬の安さではなく、費用の透明性と基準です。
相続税は評価や申告をする税理士によって、どれだけ減額できるかが異なります。
お客さまのために知見をふり絞る税理士は、ノウハウも多いため相続税が最大限に減額されますが、相続税の報酬は安くはありません。
よって、「相続税+税理士報酬」の総額が低いことがご自身や他の相続人の皆さんにとって大切なため、税理士報酬だけで決めてしまうと高い相続税を納税することになるかもしれません。
ご参考として、税務署は相続税として納税した金額が足りない場合には追徴課税などで足りない分の納税を指摘してきますが、余分に納税していた場合には一切指摘がありません。
Q6:初回の有料面談の活用方法を教えてください
相続に関して初回の有料面談を実施しているケースが多数あります。
初回面談の活用方法として最も効果的なことは相性が合うかどうかの判断です。
もちろん、財産に関わる書類や相続人に関わる書類を持参して、相続税の対象かどうかの判断や今後の流れなども教えてもらうのですが、一番はその際の話し方や配慮により、このあと継続的にお任せして一緒に進められるかの判断が必要になります。
また、当日までになるべく多くの質問事項を出しておき、紙に書いて行きましょう。
【Q&A7-8】初回有料面談の準備と相続手続きの進め方

続いて、初回の有料面談の準備と、面談後の相続手続きの進め方についてのQ&Aを確認していきましょう。
Q7:初回の有料面談時にはどのような準備が必要ですか?
初回の有料面談は通常60分程度で、この時間を最大限に活用するためには事前準備が大切です。
相続に関する書類をすべて集めてから参加するということは必要はありませんが、お手元にある資料は可能な限り持参することをおすすめします。
初回面談ではこちらの書類があると面談がスムーズに進みます。
持参した書類を見ながら専門家が状況を確認していき、持参していない必要書類については案内をしてくれます。
Q8:相談から手続き完了までどのような流れになりますか?
税理士への相談は、相続開始から2ヶ月以内を目安におこなうことが本来は望ましいのですが、四十九日の法要を過ぎていればすでに2ヶ月を経過しようとしていると思います。
相続人のみなさんで何も話していない状況で勝手に専門家へ依頼するわけにもいかないと思いますので、まずはみなさんと話をしたのちに専門家と契約をおこないましょう。
初回面談後、相続税の申告完了までの基本的な流れは次のとおりです。
相続税の申告期限は亡くなられてから10ヶ月以内と定められていますので、計画的な準備や打ち合わせをおこない余裕をもった対応が大切です。
【Q&A9-10】信頼できる専門家の選び方
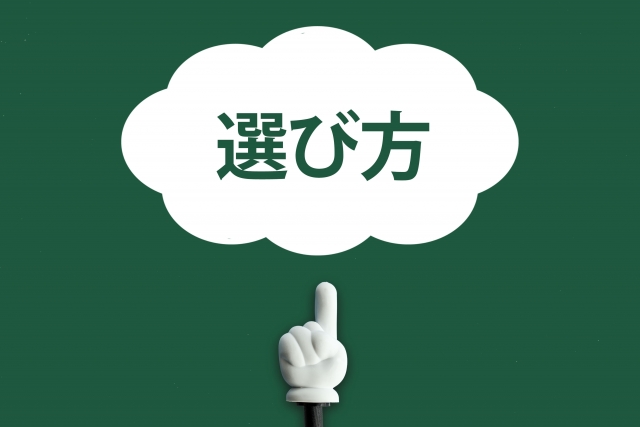
相続の相談は税理士に依頼するとよいということがお分かりいただけたと思いますが、最後は信頼できる専門家の選び方についてのQ&Aを確認していきましょう。
Q9:相続税に強い税理士の見分け方はありますか?
相続税に強い税理士は、「相続専門の税理士法人」「相続に強い税理士」などを掲げている税理士の中から選択していきます。
相続税に強い税理士は年間に10〜20件の相続税の対応をしていますので、面談の際に年間対応件数などを確認しましょう。
実績は事務所全体ではなく、ご自身の担当をしてもらえる税理士の年間対応件数の確認が大切です。
信頼できる相続税に強い税理士を選ぶためのポイントは次のとおりです。
Q10:相続税に強い税理士法人へ依頼する決め手はありますか?
相続税に強い税理士法人を上記の内容をもとに探したとしても、福岡市内には多数あります。
そんな中で最後の決め手となるポイントについて確認していきましょう。
福岡で相続の相談所と言えば税理士法人ヤマトへ
福岡で相続についてお困りの場合には、対応できる税理士法人が多数あり、税理士法人以外の専門家や企業がたくさんの広告を出しています。
そんな中で、税理士法人ヤマトは相続に強い夫婦の税理士が2人で営んでいます。
奥さまならではの視点でご支援したり、相続財産の評価で特に差が付きやすい不動産や未上場株の評価などに自信を持った対応をしています。
また、土日・祝日や平日の夜の面談も受付しており、駅チカの立地でアクセスが良いなど、相続税の支援をずっとしてきたからこそ相続に直面した方が欲しいと思う条件を揃えています。
面談料について:当法人は初回から有償(11,000円/税込・1時間、延長料金なし)で面談を実施しています。営業活動の一環としての無料面談ではなく、丁寧に時間をかけて状況を伺い、専門家としての知見をお伝えするための対価としてご理解ください。
まずは初回有料面談(11,000円/税込)にお越しいただき、相性の確認から始めませんか。