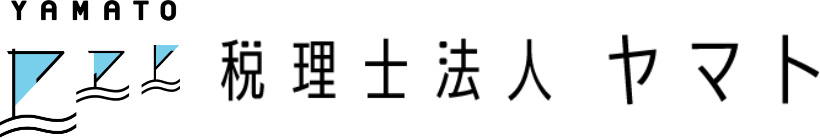Contents
旦那さまが亡くなられて葬儀の手配やその後の手続きなどを済ませていると、あっという間に1ヶ月ほど経過してしまい、相続について何も進んでいないことにご不安ではないでしょうか。
そんな時に、インターネットを検索しても税理士・司法書士・弁護士・金融機関・その他のサイトなどが並んでいて、最初にどこに相談したら良いかも分からずに、さらにお悩みになられているのではないかと思います。
本記事では、相続が発生した際に奥さまが直面する5つの悩みや、それらを解決していくためのガイドラインとなる相続の基本や手続き、相続税の概要、専門家の選び方についてご紹介していきます。
1日でも早く相続についてご安心いただくお役に立てればと思っております。
福岡での相続|配偶者が最初に直面する5つの悩み

相続の専門家は、旦那さまが亡くなられて奥さまが相続の手続きをしなければならず、どうしてよいかお困りのケースに出会うことが非常に多くあります。
最初は、具体的な相続手続きの前に、まずは生活のことや今後の進め方の全体感などを把握して安心したいお気持ちが強いかと思います。
まずは奥さまが相続手続きを進めていく際に、最初に直面する5つの悩みについて確認しましょう。
お悩み➀:相続発生直後にすべき葬儀等の手続き
亡くなられた直後に対応すべき内容は、すでにご対応済みかもしれませんが葬儀関係が7日以内、年金や健康保険の停止手続きが14日以内となります。
葬儀関係は葬儀会社が対応を代行してくれるケースもありますが、完了しているかどうかの確認をしておきましょう。
お悩み➁:配偶者が直面する生活に影響する課題
ご夫婦の生活費を旦那さまの銀行口座にしており、いつも共同で使っていらっしゃるご家族が多いかと思います。
旦那さまが亡くなられたことを金融機関が知ると、預貯金を保護するために預貯金の口座が凍結されます。
口座凍結は悪いことではなく大切な仕組みではありますが、旦那さまの口座が凍結されてしまうと生活費の確保ができなかったり、公共料金の支払いが滞るなど生活に支障が出るケースがあります。
生活費の確保やライフラインの確保なども手続きをおこなえばご不安はすぐに解消できますが、普段やらない手続きですので調べて対応するとなると大変だし時間もかかりますね。
このような生活に関わる手続きについても専門家はサポートしてくれますので、後ほどご紹介する方法等で専門家に相談しましょう。
お悩み➂:相続の全体スケジュールと期限の把握
旦那さまが亡くなられたあとの相続の手続きについては、書籍やさまざまなサイトで記載がありますので情報としてすぐに把握することができますね。
参考:相続税の申告スケジュールについてホームページに掲載されている例
亡くなられたあとから相続が完了するまでの流れを早めに把握することで、期限前に慌てることなく手続きを進めることができますので、葬儀の手続きや生活が安定し始めたら次に相続手続きの全体感を把握しましょう。
期限として意識しておくべきは、相続放棄の期限である3ヶ月と、相続税の申告期限である10ヶ月です。
これらの期限を守るために他の手続きをどのように進めていくのかという計画が大切になります。
お悩み➃:ご家族との話し合いの進め方
相続が発生した際のご家族のご状況や財産のご状況はそれぞれのご家庭で異なります。
財産の把握は奥さまお一人でも進めることができますが、遺産分割と言われる相続財産の分割についてはご家族である相続人と一緒に話し合いをおこなって全員が納得する必要があります。
誰かが自分だけ得しようとすると反対があったり、法律に沿って分割すると奥さまが今後の生活にお困りになったりと、スムーズには結論が出ないことが多いです。
ご家族が集まって相続についてお話をすると「争族」という言葉もあるように、財産の分割方法で揉めたりトラブルが発生することも珍しくありません。
大切なことは亡くなられた旦那さまのお気持ちを尊重すること、夫婦で築いてこられた大切な財産を奥さまが今後の生活に困らないように工夫することなどが大切です。
ルールを押し付けるのではなく、奥さまの立場を理解したうえでアドバイスをいただける専門家と一緒に話し合いをはじめて見ると安心ですね。
お悩み➄:福岡での相続手続き専門家の探し方
相続手続きは、教科書の替わりとなる書籍やホームページはたくさんありますが、教科書どおりに進めていけば終わるというケースは稀となります。
自分で進めてもうまくいかないケースが大半ですので、相続周りにはさまざまな専門家がいます。
福岡では、相続手続きをサポートする専門家が多数いて、専門家同士のネットワークが充実しています。
税理士、司法書士、弁護士など、各分野の専門家による総合的なサポート体制が整っているケースが多いのですが、最初に相談する窓口は相続税の申告の対象であるかどうかに関わらず税理士がおすすめです。
税理士は相続税の申告が必要となる場合には期限内に相続税の申告が終わるように他の専門家と相談しながら段取りを進めてくれますし、相続税の申告の対象とならない場合にも日ごろから一緒に活動している専門家を紹介してもらうことができますので、もう一度探しなおす手間などもなくスムーズに進めていくことができます。
面談料について:税理士業界では「初回無料」と掲げる事務所も多くございますが、税理士法人ヤマトでは「ご相談に全力で対応する」覚悟をお示しするために、あえて有償(11,000円/税込)の面談とさせていただいております。
営業活動の一環としての無料面談ではなく、目の前のお客様の不安や期待に正面から向き合い、専門家としての知見をお伝えするための対価としてご理解いただければ幸いです。※面談時間は1時間を予定しておりますが、時間を超過しても追加料金は頂戴しておりません。
有料面談では、ここまでご紹介した悩みを解決するための道筋や優先順位を具体的に整理し、初回から実務的なアドバイスをご提供します。
そんなときは、夫婦で相続手続きをサポートする税理士法人ヤマトへのご相談がおすすめです。
夫婦の税理士が直接対応をしていますので、ご夫婦ならではの悩みや奥さまが相談しづらい内容も、奥さま目線でのサポートを心がけていますので安心してお話しいただけると思います。
初回から有償の面談となりますが、土日の対応や平日の夜の対応も受付しており、ご家族が集まれる大切な時間に合わせて一緒に進めることができます。
相続手続きの基本|3ヶ月以内に確認すべき重要ポイント

相続手続きを進める上で、最初の3ヶ月以内に確認しておくと良い内容について整理しました。
この期間で最も大切なことは相続放棄をするかどうかという重大な決断をすることになりますが、この判断のためには相続手続きの基本となる内容について明確にする必要があります。
葬儀が終わり四十九日の法要が終わったころには1.5ヶ月が経過していますので、四十九日を終えているようでしたら気持ち的にも少し落ち着いたところではあると思いますが、相続放棄の判断をする期限まで残り1.5ヶ月ですのであらためてがんばっていきましょう。
基本①:相続人の確認と法定相続分
相続手続きの最初のステップは、今回の相続において誰が相続人となるのか、相続人となる方が何人いるのかを把握します。
相続人が誰であるか、相続人が何人かが分かると、相続の分割をする際の基準となる法定相続分が明確になりますので、このあと誰とどのような相続財産の分割の話をすればよいかがわかります。
法定相続分は、配偶者は常に相続人となり、子どもがいる場合は配偶者が財産の2分の1、子供たちで残りの2分の1を分割するというような相続財産を分割する際の基本となるルールです。
もう1点は相続放棄をする場合には、相続人となる方には全員へ正しく情報を伝えて、それぞれに相続放棄の手続きをしてもらう必要もあります。
基本②:相続財産の調査方法
続いて、相続財産の調査をおこないます。
相続財産は、預貯金、不動産、有価証券といったプラスの財産から、借金などのマイナス財産、そして生命保険などのみなし財産と言われている財産をすべて明確にする必要があります。
亡くなられた方の通帳や契約書類の確認をおこない財産を調査するだけでなく、場合によっては税務署や法務局での調査も必要となるケースもあります。
最終的にはすべてを正しく把握する必要がありますが、この時点では特に借金の有無を重点的に把握することが優先であり、相続財産を受け入れるのか、放棄をするのか決める材料が必要となります。
基本③:相続放棄の検討と期限
少し目線を変えて、亡くなられた日から3ヶ月以内に判断が必要となる相続放棄について確認します。
相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述するというルールがあります。
相続開始を知った日とありますが、一緒に生活しているご家族や葬儀に出席した相続人の皆さんは、葬儀に出席した時点で相続が発生したと知ることになりますので、多くの場合には亡くなられた日から3ヶ月が期限となりますね。
音信不通で連絡を取っていなかった家族が、亡くなったことなどを知らず、相続の存在を知らなかったケースなど、特別な事情がある場合は期限後でも相続放棄が認められることがあります。
相続をする方の大半は相続財産を正しく把握しなくても相続をすることを選択することになりますが、いずれやらないといけないことでもあり、もしものことがあるといけないためこの3ヶ月の期限を節目に、相続財産の把握や、相続人の確定をしておきましょう。
相続手続きの完了まで|相続人が準備すべき書類や手順

相続放棄をするかどうかを判断したあと、相続財産を相続することを決めたら次に相続手続きを完了させていくための手続きをしていきます。
相続手続きの中には複雑なものや、専門的な知識を必要とするものもありますし、手続きをおこなう前には相続人全員から財産の分割について合意を得る必要があります。
相続税の申告が必要な場合には、書類を準備したり分割について協議したりするなど早めの対応が大切になりますので、調べながらだと大変ですので専門家に頼りながら進めていくことをおすすめします。
必要書類の収集方法
相続財産を把握する際にある程度の収集を終えているかもしれませんが、必要書類をすべて揃える必要がありますので必要書類をリスト化して抜け漏れが無いように収集しましょう。
財産によって収集する必要書類が変わりますが、主には戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書などの公的書類を市区町村の窓口で取得します。
その他に預貯金の残高証明書や不動産の登記事項証明書なども、金融機関や法務局で取得していきます。
遺産分割協議書の作成手順
相続財産をどのように分割するか決めたあと、全員が合意したことを示すために遺産分割協議書という書類を作成して全員が署名・捺印をします。
この遺産分割協議書に全員の押印が無いと、相続財産の名義変更や相続税の申告ができません。
最初の3ヶ月で相続人を把握したことで相続財産の分割の基準となる法定相続分が分かりますので、この法定相続分と相続財産を見ながら、どのような分割をおこなうと相続人にとって良いのかを調整していきます。
旦那さまが亡くなられて奥さまが自宅を相続すると、生活するための現金が無くなる。というケースもありますので、法定相続分を基準としながら調整をしていくことが大切になります。
相続人は自己主張をしがちですが、亡くなられた方のお気持ちを大切にするのが相続の基本ですので、生前にお話をしていたらどのようなお気持ちで話をされるのかなども考えていけると良い相続につながります。
一方で、奥さまがすべての財産を相続すると、奥さまが亡くなられた際にお子さまが相続の際に大変になるケースもありますので、次の相続を想定しておくことも大切です。
相続登記等の名義変更を進める
相続登記は、不動産の名義変更をおこなう手続きになります。
登記申請には、申請書のほか遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書などが必要となります。
これらの書類を集めて法務局で手続きをしますが、こちらも専門家へまとめてお願いすることが得策です。
その他、金融機関の凍結された口座の解除のための手続きもおこなっていきます。
金融機関によって異なりますが、相続人全員の署名・捺印を求められるケースや、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明があれば対応してもらえるケースもあります。
各金融機関で手続きを確認して進めていくと良いですが、不動産の相続登記等と一緒に専門家に依頼した方がスムーズです。
相続手続き完了後の確認事項
相続手続き完了後は、金融機関口座の名義や不動産の名義などが変わっているかどうか忘れずに確認しておきましょう。
不動産は法務局で登記事項証明書を取得すれば名義変更の完了を確認できますが、専門家に依頼していればこちらの証明書を取得して届けてくれるケースが多いかと思います。
相続税と配偶者控除|専門家が解説する重要事項

相続手続きを進めていく中で遺産分割協議書を作成しました。
遺産分割協議書ができたことで、すべての財産が把握できその分割についても相続人全員と合意できたことになります。
すべての財産が分かると相続財産の総額が、基礎控除といわれる相続税の申告をするかどうかの基準よりも財産が多いかどうかを確認することで相続税の対象かどうか判断が可能です。
この基礎控除は、相続人の数によっても変わってきますが「3,000万円+(600万円✕相続人の数)」という式で確認できますので、ご自身でもおおよそ対象かどうかを確認することができます。
相続税の申告対象となる場合には、申告書を作成していきますが相続税を減額する制度などがありますので、相続税に強い税理士に依頼することが得策となります。
配偶者控除の基本的な仕組み
旦那さまが亡くなられた際に奥さまに適用される配偶者控除という、配偶者だけが受けられる特別な控除があります。
この配偶者控除は、配偶者が相続した財産が1億6,000万円以下、または法定相続分相当のいずれか多い金額まで相続税がかからない制度です。
この制度を利用するには、戸籍上の配偶者であることや、相続税の申告期限までに遺産分割を完了していることが条件となりますので、配偶者の方が相続をする場合には相続税が発生しないケースが多くなります。
ただし、この制度を使って全額を相続することで相続税をゼロ円にしてしまうと、お子さんへの相続の際に困るケースも多々ありますので、専門家とよく相談しましょう。
その他の活用できる税制優遇制度
配偶者控除の他には、相続税の計算対象となる不動産の評価額を最大80%減額できる小規模宅地等の特例や、生命保険等の非課税枠などの相続税の納税額を減額できる制度が多数あります。
適用条件の確認など複雑な要件が多数ありますし、どんな制度があるのかを全て確認するのはとても大変ですが、相続に強い税理士は日ごろから相続手続きを多数対応していることから経験やノウハウがあり、制度にも熟知しています。
相続財産の評価
相続税の計算をする際には、財産の実際の価値ではなく、相続税の財産評価の方法に応じて再計算した結果を使用します。
預貯金や生命保険などは額面通りですが、不動産のなかでも特に土地の評価や、未上場株を持っている場合にはその株価評価は知見によって考え方が異なり大きく差が開くケースがあります。
例えば不動産は土地の形状が長方形であったり、近隣施設の影響があったりする場所では、相続税の評価額を減額できるのですが、実際の土地を見たり、より多くの知見が無いと減額できるはずの要件を見落としてしまうケースもあります。
相続税に強い税理士は日々相続に関わる対応をしていますので、減額できる知見にも自信があり、しっかりとした評価結果を基に相続税の申告をしていますので、相続税に強い税理士の選択が最もメリットとなる部分です。
相続税の計算方法と申告期限
相続税の申告は、亡くなられた日の翌日から10ヶ月以内におこなう必要があります。
この申告期限を過ぎると、配偶者控除などの税制優遇が受けられなくなる可能性があるだけでなく、延滞税や加算税などのペナルティがあるため、期限内に提出しないリスクが大きいため、期限内に申告できるように努力しましょう。
期限を過ぎてしまうケースとして、相続手続きの開始が遅いケースや、すでに記載している遺産分割協議書の分割内容がいつまでも合意されないケースなどがあります。
誰もが余分な納税をしたいと思っていないはずですので、もし話し合いがまとまらない場合には相続人の皆さんへ期限内に申告できないリスクについても説明しておきましょう。
相続の専門家選び|福岡で信頼できる相談先の見つけ方

全国には相続に関する専門家が多数いますし、福岡のエリアにも同様に多数の専門家がおり、相続に特化した税理士法人や会計事務所も集中しています。
今回の記事を通じて最初に税理士を選択するとスムーズに進んでいくことも納得いただけたのではないでしょうか。
相続手続きと相続税の申告を進めていく上でのポイントをあらためて整理しましょう。
・相続財産の把握
・相続財産の分割方法の検討
・相続税の申告が必要かどうかの判断
・相続税の申告で使える特例の判断
・相続税の申告書の作成
上記の内容を進めていくときに、誰と一緒に進めていくと安心かを想像してみてください。
財産の分割の話などスムーズに進むとも限りませんので、奥さまと同じ目線でサポートしてくれる専門家がいたら一番安心ではないでしょうか。
インターネットなどではさまざまな税理士や税理士法人がありますが、最初の相談から手続きや申告の完了、そのあとのサポートまで一貫して専門の税理士が対応してもらえたらさらに安心です。
税理士法人ヤマトは夫婦税理士で運営しており、夫婦税理士が自ら対応する税理士法人です。
大手税理士法人の場合には税理士以外の方が対応して最後は税理士がチェックするなどのケースも多いですが、直接税理士に相談することができる点はとても安心ですね。
また、初回から有償の面談ですが、土日の対応や平日の夜の対応も受付しており、ご家族が集まれる大切な時間に合わせて一緒にすすめることができます。
もちろん、相続税に強い税理士法人ですので、相続税の申告に長けており知識も豊富です。
もし、福岡周辺で相続が発生してどのように進めて良いか悩まれているようでしたら、まずは税理士法人ヤマトへ相談してみてはいかがでしょうか。